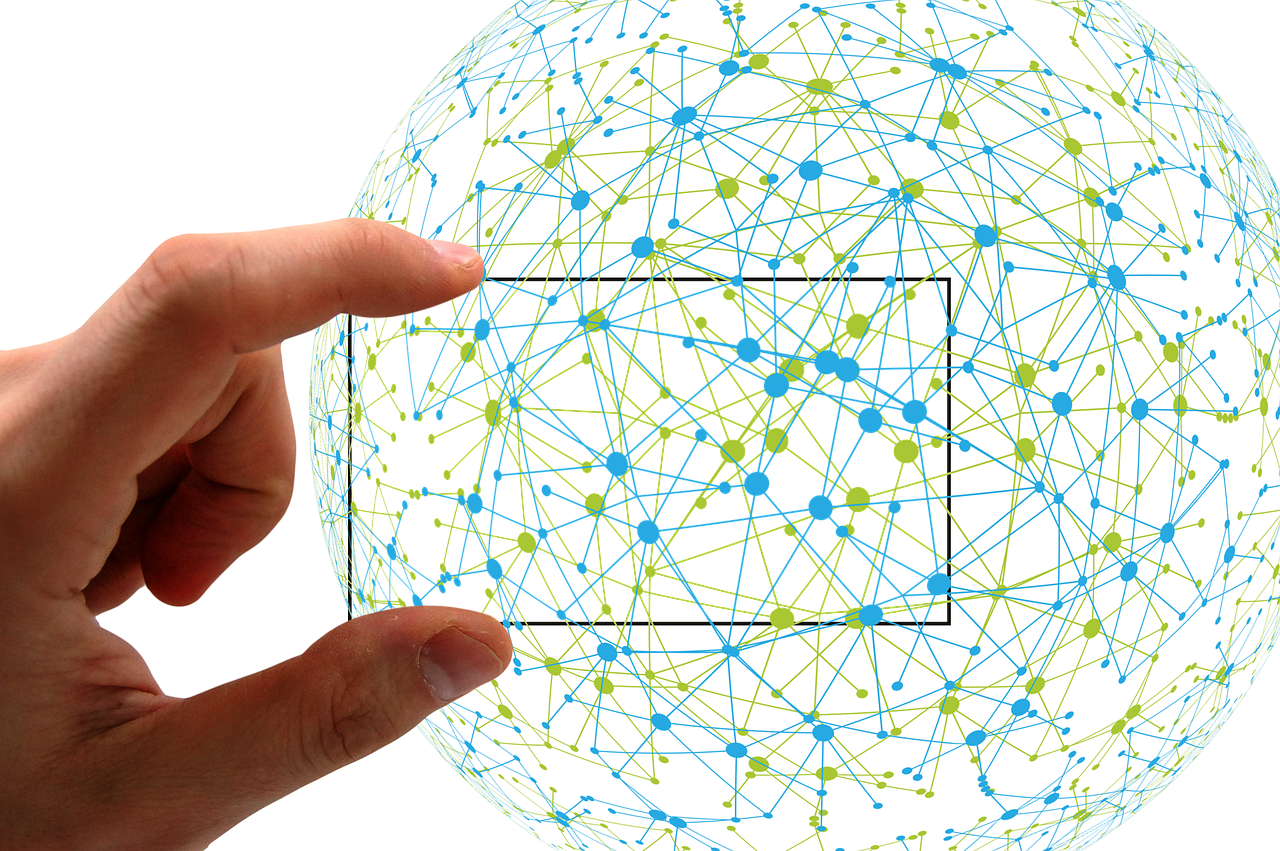DXとは?注目されている背景や企業の現状とともに解説します!
デジタルトランスフォーメーション(DX)は今や現代社会に欠かせない概念であり、今後も重要になってきます。実際に成功例も多く、日本においても行政がデジタルトランスフォーメーションを積極的に推進しています。そもそもデジタルトランスフォーメーションとは一体どんな内容の言葉なのでしょうか。この記事では定義や具体的な事例、今後直面するであろう問題まで徹底解説します!
目次 [閉じる]
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは
DX(Digital Transformation/デジタルトランスフォーメーション)とは、2004年にスウェーデンのウメオ大学教授、エリック・ストルターマン氏によって提唱された概念です。
この概念には、「進化したIT技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革させる」という意味があります。
以下で詳しく解説します。
経済産業省の定義
経済産業省によると、定義は下記のようになっています。
狭義:社会のデジタル化
DXはもともと、ITの浸透が人々の生活をより良い方向に進ませるという概念として登場しました。
すなわち、社会のデジタル化によって人々の暮らしがより良くなるというものです。
広義:ビジネスのデジタル化
経済産業省によると、広義での定義は下記のようになっています。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
つまり、経済産業省の提唱したDXの定義はビジネスのデジタル化による業務や業績などの向上、改善ということになります。
ビジネスシーンで考えて簡潔に言い表すと、「データやデジタル技術を駆使して、ビジネス全体を根底から変革し、人々の生活をより良いものにしましょう」ということです。
デジタル技術を駆使して新たな製品・サービスを生み出して人々に貢献することはもちろん、既存ビジネスの生産性向上やコスト・時間の削減を目標にしています。
さらに、それを実現させるために経営戦略やビジョンの明確化、ビジネスモデルや組織のあり方自体の見直しが求められています。
目まぐるしくデジタル技術が発展する中で、迅速な環境変化への対応や、企業文化の変革こそが、今後企業が取り組むべきDXの課題となっています。
デジタイゼーション・デジタライゼーションとの違い
DX(Digital Transformation/デジタルトランスフォーメーション)と「デジタイゼーション(Digitization)」、「デジタライゼーション(Digitalization)」はよく混同されがちですが、意味が異なります。
「デジタイゼーション(Digitization)」は、単に仕事の効率化のためのデジタル化のことを表します。
極めて部分的に限定されたものを示していることがわかります。
「デジタライゼーション(Digitalization)」は、長期的に環境面やビジネス戦略面を考え、デジタル化する取り組みのことを言います。
デジタル技術を駆使し、新たな価値を生み出すというのは、より他社やユーザーとの関わりに視野を広げていることがわかります。
一方でDX(Digital Transformation/デジタルトランスフォーメーション)は、「デジタル技術によって人々の生活をより良いものへと変革する」という意味合いが強く、導入したデジタル技術の革新によって社会にどんな影響をもたらすかということを表します。
つまり、アナログからデジタルにかさせることを「デジタイゼーション」、
デジタルを駆使ししてさらにビジネスを発展させることを「デジタイゼーション」、
そしてこの2つの結果として社会にもたらす影響のことを「DX(Digital Transformation/デジタルトランスフォーメーション)」というわけです。
IT化とDXの関係性
DXはIT化ともよく混同されます。
IT(Information Technology(インフォメーションテクノロジー))化というのは、これまでアナログで行ってきた作業をデジタルに変換し、作業効率をあげる取り組みのことを表します。極めて部分的に限定されたものを示していて、「デジタイゼーション」と基本的に意味は同じです。
そのため、IT化の延長線上にDXがあると考えてください。
ITはデジタル化することを「目的」とし、DXはデジタル化することを「手段」としてその先を考えています。
つまりDXというのは、IT化を取り入れた結果、人々の生活をどのように豊かにできるか、社会にどのような影響を与えられるかを考えて、さらなる企業改革を行う仕組みや体制のことであると言えます。
DXが注目されている背景
ここではDXが注目されるようになった背景を紹介していきます。
2025年の崖
DXが注目されるようになった要因の中で特に大きく作用したのが「2025年の崖」と呼ばれる問題です。
経済産業省が発表した「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」によると、この問題は既存のシステムの抱える問題を2025年までに解決できなければ、以後は年間12兆円にも及ぶ損失になると予想されています。
老朽化したシステムや複雑化したシステムを放置すると、最先端のデジタル技術を取り入れたところで全く効果を発揮できなくなってしまいます。また、保守・運用にかかるコストも膨大です。
もしこうなれば、DXに乗り遅れるだけでは済みません。最悪の場合、自社のシステムを維持できなってしまう危険性もあります。
また、部門ごとにシステムが独立していて、部門を超えたデータ共有や活用などが全くできないという課題も2025年までに解決すべき課題として指摘されています。
デジタル化に伴うビジネスの多様化
デジタル化によってビジネスも多様化しています。
これは、新規参入してきた企業がデジタル技術を駆使し、これまでになかった新しいサービスや商品を次々と生み出していることが原因です。
このように、DXはビジネスの多様化や新規事業の立ち上げを促進している側面がありますが、実はそれだけにとどまりません。
生産性向上やコスト・時間の削減といった既存領域の成長のための変革にも、DXは役に立っています。
消費者ニーズの変化
DXが注目される背景に消費者ニーズの変化も関わっています。
数年前までは店舗に足を運んで購入していた物も、今ではインターネットで購入するのが当たり前となりました。衣類の購入を例に挙げると、以前までは実店舗に行ってサイズを確認して購入するのが当たり前でした。
ところがデジタル化が進んだ今、自宅でもサイズを図ることができるシステムが提供されるようになり、その結果として消費者はインターネットで衣類を購入するのが当たり前となっています。
「インターネット販売サイトで購入したい」という消費者のニーズに応えるためには、当然デジタル化する必要があります。
このような消費者ニーズの変化が、DXを推進させるきっかけとなっています。
新型コロナウィルスの流行
2020年から世界中で流行した新型コロナウィルスもDXを促進させるきっかけとなりました。
これは、感染対策として自宅での生活を余儀なくされたことが原因として挙げられます。
例えば、テレワークやオンライン授業など、デジタルを多用した働き方や暮らしへと大きく変化しました。
新型コロナウィルスに限らず、社会問題はDXを促進させるきっかけとなります。
いつ再び大規模なウィルスの流行や災害が起きるかが予測できないため、今後の想定外の変化に備えてDXに踏み切る必要があります。
DX推進に向けた現状の課題
消費者のニーズに応えるため、また社会の流れに乗り遅れないためにもDXへの取り組みは不可欠です。
現在の日本企業の多くはDXの必要性を認識し、DXを進めるためにデジタル部門を設置する等の取り組みが行われています。
しかし、実際のビジネス変革には繋がっていないという状況が多いのが現状です。
そこで、具体的にどういった課題を抱えているのかを紹介します。
老朽化したシステムによるDXの足かせ
老朽化したシステムをそのままにした状態でDXを行おうとすると効果は発揮されません。
むしろ、足かせとなってしまいます。
老朽化したシステムは複雑化していることが多く、当時の担当者出なければ解決できない場合があるからです。
DXを実現するためには、大前提としてITシステムの基盤を構築する必要があります。
もし修正が効かないほどシステムが老巧化している場合は、システムを一から刷新してDXを行うことも考えましょう。
IT人材の確保
昨今、労働人口は減少してします。IT人材も例外ではありません。
DXを推進するにあたり、デジタル分野などに詳しいIT人材は必須です。
具体的に、確保すべきIT人材は以下の通りです。
・プロデューサー(DXを主導するリーダー格の人材)
・アーキテクト(システムを設計できる人材)
・ビジネスデザイナー(DXの企画・立案・推進等を担う人材)
・データサイエンティスト・AIエンジニア(デジタル技術やデータ解析に精通した人材)
・UXデザイナー(システムのユーザー向けデザインを担当する人材)
・エンジニア・プログラマ(上記以外にデジタルシステムの実装やインフラ構築などを担う人材)
しかし、IT人材をめぐる獲得競争も熾烈を極めており、十分に確保できなければDXの流れに乗ることは難しくなってしまいます。
デジタル領域に精通し、率先して事業を変革できる知見・スキルを所持している人材の確保が難しいのが現状です。
DXに関する曖昧な経営戦略
DXを実行するにあたり、明確な経営戦略やビジョンを持つことが大切です。
しかし、DXについて社内で明確なビジョンがないという企業も多いのが現状です。
多くの企業が、PoC(Proof of Concept: 概念実証、新しいプロジェクト全体を作り上げる前に実施する戦略仮説・コンセプトの検証工程)は繰り返し行なっているものの、実際のビジネス変革には繋がっていません。
また、部下に「AIを使って何かしてほしい」という曖昧な指示で丸投げしている企業も多いのが現状です。
経営トップ自らが、ビジネスや仕事の仕方、組織・人事の仕組み、企業文化・風土そのものの変革に強いコミットメントを持って取り組む必要があります。
その際、変革に対する社内での抵抗が大きい場合には、経営者がリーダーシップを発揮し、意思決定することが大切です。
\ IT転職のプロが無料でサポート! /
DXの事例をご紹介
最後に、DXの事例を紹介していきます。
ここではメルカリ、株式会社ユニメイト、Netflix、NECの事例をピックアップして紹介します。
事例①メルカリ
メルカリは、今やCtoCビジネスの中心的位置を獲得しています。
メルカリが普及する前、CtoCビジネスと言えばオークション形式のサイトが主流でしが、ユーザーの抱えていた不満からビジネスの課題を見つけ、デジタル技術の活用によって改善しようとしたのがメルカリです。
メルカリのDXへの取り組み事例
メルカリはまず、心理的負担を軽減するためにフリーマーケット形式を採用しました。
フリーマーケットは売り手が価格を設定し、買い手は交渉次第で値下げすることができます。オークション形式よりも気軽に出品できるという利点があります。
また、スマホからでも出品できるようなユーザーインターフェースを開発し、いつでもどこでも気軽に出品できるという環境を実現しました。
DXによりえられた成果
「フリマアプリと言えば、メルカリ」と言われるほどの認知度を獲得し、国内で8000万超、世界全体で1億を超えるダウンロード数を誇っています。
また、日本初のユニコーン企業(非上場で企業価値10ドル超のテクノロジー企業)となるまでに至りました。
事例②株式会社ユニメイト
続いて紹介するのはレンタルユニフォームの事業を手掛けている株式会社ユニメイトの事例です。
従来ではクライアントが自己申告でサイズを申請する仕組みでしたが、ヒューマンエラーによるサイズ違いが相次いでいたことが課題でした。
サイズ違いが相次いだことで返品・交換コストが発生していたため、これらのコストを抑えるためにも効率化する必要性に迫られていました。
ユニメイトのDXへの取り組み
ユニメイトはAI画像認識によってAIが自動的にサイズを採寸する『AI×R Tailor(エアテイラー)』を開発しました。
これにより、サイズ違いによる返品作業などユーザーの負担を軽減するだけでなく、輸送などの無駄な費用も削減することに成功しています。
DXによりえられた成果
『AI×R Tailor(エアテイラー)』は、コロナの影響と相まって思わぬところでも反響を呼びました。
例えば、学生服や制服の採寸などです。
以前は手作業で採寸を行なっていましたが、コロナの影響により3密を避けなければなりませんでした。
そこで『AI×R Tailor(エアテイラー)』を利用するようになったわけです。
このようにユニメイトは、時代にあった新たなニーズを獲得することができています。
事例③Netflix
Netflixは、アメリカの大手動画配信サービスです。
今でこそ誰もが知っているVODサイトとなりましたが、元々はDVDを郵送レンタルする事業からスタートしました。
NetflixのDXへの取り組み
2007年に、CEOのリード・ヘイスティングス(Reed Hastings)が、新技術であるストリーミングサービス(インターネット接続を通してその都度映像や音楽を受信する技術を用いたサービス)に目をつけました。
当時好調だったDVDレンタル事業から、ストリーミングでの映画配信事業に完全に移行したのです。
Netflixは、以前から時代や顧客のニーズに合わせて事業を変化させています。
過去4度にわたる革新の末、現在のストリーミングサービスを取り入れることになりました。
DXにより得られた成果
現在では、ネットフリックス(Netflix)は世界で2億人、日本では500万人以上の有料会員が利用しています。
多額の費用をかけオリジナルコンテンツも作成するようになった結果、ネットフリックスは世界中へシェアを拡大していきました。
事例④日本電気株式会社(NEC)
日本電気株式会社(NEC)は、社会公共事業、社会基盤事業、エンタープライズ事業、ネットワークサービス事業、グローバル事業と多岐にわたって事業を取り組んでいます。
NECが行ったDXと、それにより得られた成果を紹介します。
NECのDXへの取り組み
日本電気株式会社(NEC)は、世界トップクラスの生体認証技術などの最先端のデジタル技術を活かしたDX事業を展開しています。そのほか、DXサプライヤーとしての対応も進めています。
新型コロナウイルス蔓延を受けた緊急事態宣言発令後、NECグループの6万人以上の社員が円滑にテレワークに移行し、スムーズな業務継続を実現しました。
DXにより得られた成果
同社はDXへの取り組みの結果、経済産業省と東京証券取引所が選定する「デジタルトランスフォーメーション(DX)銘柄2021」と「デジタル×コロナ対策企業(レジリエンス部門)」に選定されました。
また、今年度は新型コロナウイルス感染症を踏まえた対応に関して、デジタル技術を利用して優れた取り組みを実施したとして、「デジタル×コロナ対策企業」として選定されました。
まとめ
DXは社会に様々な変化をもたらします。
社会のデジタル化や自動化はもちろん、ビジネスにおいては効率化や新規事業など、様々な可能性に満ちています。さらに、各企業はDXに携わる人材を求めています。
DXに関わってみたい、そんな方はIT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントであるギークリーにご相談ください。
ギークリーではDXに関する求人を多数保有しております。ご相談ベースからでも承っておりますので、お気軽にご登録ください。
\ IT転職のプロが無料でサポート! /
あわせて読みたい関連記事
新着記事はこちら
-
- AI企業ランキング日本版!売上高・平均年収・離職率トップ5は?
-
2025/4/1
- AI
- ランキング
- 業界紹介
-
- 「SKYFLAGを世界一のプロダクトへ」挑戦を続けるSkyfallのプロダクト本部が語る今後の展望とは
-
2025/3/28
- 事業インタビュー
- 株式会社Skyfall
- 特集
-
- 【アンケート調査】今の会社を選んだ理由や、企業選びで重視する要素とは?
-
2025/3/28
- IT転職
- アンケート調査
- 特集
-
- なぜ書類選考で落ちた?ショックを受けなくても大丈夫な理由を解説
-
2025/3/27
- IT転職
- 書類選考
- 転職ノウハウ
-
- 技術だけでは終わらせない。事業と会社を動かすエンジニアの挑戦。新しい価値を生み出し、会社の未来を創る。ナハトでのエンジニアの働き方とは
-
2025/3/17
- 事業インタビュー
- 株式会社ナハト
- 特集
-
- インフラエンジニアの自己PR例文|経験者・未経験者向けの書き方やポイントを解説
-
2025/2/28
- IT転職
- インフラエンジニア
- 職種解説


 関連リンク
関連リンク