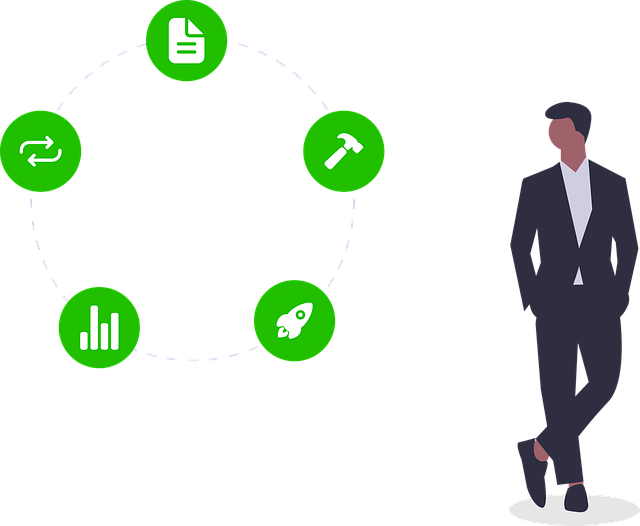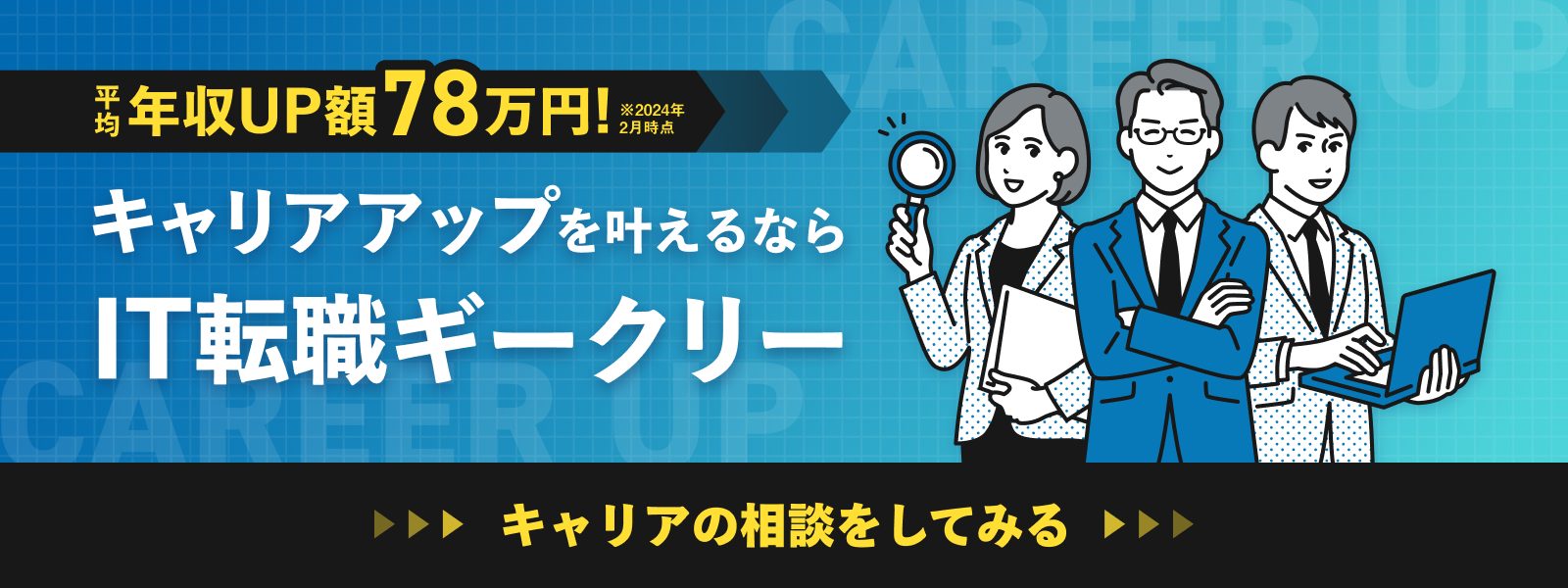メディアリテラシーの具体例9つ!意味や身につける必要性を解説
この記事では、メディアリテラシーの具体例について解説します。現代社会ではなぜメディアリテラシーが必要とされているのでしょうか。自分が接する情報を正しく評価し、信頼できる情報源を見極める力が大切な理由を把握して、実践方法を役立てましょう。
目次 [閉じる]
メディアリテラシーの意味をわかりやすく解説
メディアリテラシー=手に入れた情報を取捨選択するスキル
メディアリテラシーとは「メディアから得た情報を見極めるスキル」、つまり「メディアの情報をそのまま受け取るのではなく、自分で考え確認するスキル」です。
情報リテラシーやネットリテラシーといった言葉とほぼ同じ意味で使われています。
特に不特定多数が発信者とも受信者ともなりうる現代では、メディアリテラシーが十分に養われていないと間違った情報に踊らされるリスクが格段に上昇してしまいます。
メディアから得た情報を主体的に判読し、活用することが大切です。
メディアの情報を額面通りに受け取らない
新聞やテレビなどのマスメディアからの情報はもちろん、ミクロ単位で発信された情報も完全に正しいデータとは限らない点では共通です。
必要な情報を集める際には以下の2点を心がけましょう。
・真偽や信憑性の高さの確認
・その情報を信じた場合のメリット・デメリットの検討
客観性に欠けるため参考にならない、発信された情報が全データのうちのほんの一部といったケース以外にも、そもそもデータ自体が間違っていたり存在しない場合もあります。
いずれにしても、そのまま受け取らずに主体的に調べてから理解するようにしましょう。
\ IT業界・職種の最新情報が満載! /
メディアリテラシーはなぜ必要?
メディアリテラシーを身につける必要性について、さらに掘り下げて解説します。
①真偽不明の情報が溢れているため
②伝える媒体によって情報の内容が偏るため
③情報の発信や拡散が容易に行えるため
メディアリテラシーが必要な理由を把握して、実生活や仕事に役立てましょう。
①真偽不明の情報が溢れているため
現代では、何かわからないことがあればブラウザで検索をすればたくさんの情報が得られます。
しかし、出てきた情報が全て正しいとは限りません。その情報が正しいかどうかを一目で判断することは困難です。
だからこそ、真偽が分からない情報はとりあえず疑う姿勢が求められます。
「どうせ真偽不明だから信じる」よりも、「真偽不明だからひとまず信じない」の方が被害は抑えられるためです。
情報の真偽がわからないときは、次のような確認方法がおすすめです。
・専門機関や関連企業等のサイトで情報を確認する
・時間帯と内容次第では直接問い合わせる
・信頼できる情報を整理する
緊急性に応じて上記のようなアクションをとり、不確かな情報に惑わされないようにしましょう。
②伝える媒体によって情報の内容が偏るため
情報自体が間違っていなくても、立場や視点の違いから内容が異なるケースも多々あります。
例えば「20年前より就職率は上昇したが、ここ3年は連続して下降している」という情報があったとします。
これを「長期的な傾向に焦点をあてているメディアA」と「最近の動向に注目しているメディアB」が報じるとなると、下記のような表記の違いが予想されます。
- メディアA:就職率、20年前より〇%上昇
- メディアB:就職率、3年連続下降
どちらも真実ではありますが、どの部分を切り取るかによって印象が大きく異なることがわかります。
もしメディアAの情報だけを信じてしまうと、「最近は就職しやすくなっている」という誤った認識に至ってしまうかもしれません。
このようにメディアリテラシーの有無によって、必要な情報を正確な形で手に入れられるかどうかは大きく左右されるのが、メディアリテラシーが必要な理由です。
③情報の発信や拡散が容易に行えるため
インターネットやSNSの普及に伴い、多くの人々が主体性をもって情報を発信・拡散することが可能になりました。
その一方で、不確定な情報の拡散や個人への攻撃へのハードルも低くなっています。
確かに情報共有が容易だと、必要な情報が多くの人の目に止まりやすくなるでしょう。
しかし、詳しいことがわからないまま情報を広めてしまったために、誰かを傷つけてしまったり、犯罪に繋がるケースもあります。
例えば落とし物の情報を善意で拡散したものの、実際に受け取りに来た相手は本人を装った別人だったということもあり得るでしょう。
「困っているだろう」と思い遣る気持ちと同様に、その善意が悪用される可能性も頭の中に入れておくことも大切です。
情報をネットの海に流す前に、少し立ち止まって「これは本当に多くの人に見せてもよい情報なのだろうか」と考えることがメディアリテラシーです。
\ IT転職のプロが無料でサポート! /
メディアリテラシーが必要な場面の具体例4つ
メディアリテラシーが必要とされる場面の具体例を4つ解説します。
・仕事で資料を作成するとき
・人の命や尊厳に深く関わる情報を得るとき
・誰かの個人情報に触れたとき
・悪質な広告や詐欺を見抜く必要があるとき
いずれも日常生活で触れることが多い場面です。
メディアリテラシーをより深く理解するために、参考にしましょう。
仕事で資料を作成するとき
メディアリテラシーの有無は、ビジネスマンとしての能力や成果に影響を与えます。
例えば顧客向けにプレゼンをしなければならない時や、上司向けの提案資料を作成する時といった日常的な場面でも、メディアリテラシーは求められるためです。
信用のおける機関が実施した調査をもとに作成した資料と、まとめ記事に載っていた情報をもとに作成した資料では、情報の正確性や信頼性には大きな差があります。
その結果として、提案が通るかどうかといった重要な面にも大きく作用するでしょう。
人の命や尊厳に深く関わる情報を得るとき
医療などの、人の命や尊厳に直結する情報はメディアリテラシーが求められる最たる例と言っても過言ではないでしょう。
たとえ「専門家」と自称していても、ネット上では本当かどうかわかりません。
また、相談する人の実際の状態や取り巻く環境を把握せずに、適切なアドバイスをすることはほぼ不可能であると認識しておきましょう。
正しい情報を集めたるためには、情報源の信頼性にも重きを置くことが大切です。
また、誹謗中傷のおそれがある情報や、根拠が曖昧な批判などは鵜呑みにしないようにしましょう。
場合によっては相手の尊厳を踏みにじり、相手の存在そのものを否定することにも繋がる危険性があります。
インパクトのある文章や簡潔な語り口に惑わされず、「その情報は何を根拠にしているのか」「見方が偏っていないか」といった情報の中身をしっかりチェックしましょう。
誰かの個人情報に触れたとき
各種SNSなどでたくさんの人々がプライベートの情報をアップロードする時代では、偶然友人知人の個人情報を目にする機会も増えています。
メディアリテラシーの観点では、その情報の扱いにも注意が必要です。
例えばSNSで自分の写真付きの近況を報告している友人の投稿を同じSNS内で共有するのは問題ありませんが、無断で他のSNSにアップロードするのはNGです。
情報を共有したいという親切心からの行いであったとしても、プライバシーと肖像権の侵害にあたる可能性があります。
本人の意思に反して、勝手に個人情報を広めるのは避けましょう。
悪質な広告や詐欺を見抜く必要があるとき
Webサイトやメールには「当選おめでとうございます」「○○ポイントが間もなく失効します」「無料プレゼント」といったクリックを促すようなものが多くあります。
しかし実際はマルウェアに感染させたり、IDやパスワードなどの情報を盗むことが目的の場合が多いです。
近年はSMSなどで「不正アクセスがありました」「パスワードの復旧が必要です」というように緊急を要すると勘違いさせるメッセージも多用されているようです。
普段使用しているクレジットカード会社や銀行、携帯会社、電気・ガス・水道などのインフラ企業を装った差出人からのメールは開封してURLをクリックしてしまわないよう注意しましょう。
気になるメッセージが届いた場合は、その発信元が同様の注意喚起をメールで行っているのか1度確認することが大切です。
\ IT転職のプロが無料でサポート! /
メディアリテラシーの欠如による弊害の具体例5つ
メディアリテラシーが欠如していると起こりえるリスクについて、具体例には次のようなものがあります。
・誤情報の拡散
・情報に踊らされてしまう
・誹謗中傷によるトラブル
・情報漏洩
・個人情報の特定
以下、詳しく解説します。
誤情報の拡散
メディアリテラシーの欠如は、間違った情報の再生産に繋がりかねません。
根も葉もない噂話程度のものだったとしても、不特定多数が何の疑問も持たずに拡散してしまえば、あたかも「事実」のように語られてしまう可能性すらあります。
信憑性に欠ける情報が増えるにつれて、信憑性の高い情報が埋もれてしまいやすく、結果として必要な情報が必要としている人に届きにくい環境を生み出してしまいます。
また、誤った情報を拡散することによって、個人や企業の信頼性の低下やトラブルを引き起こすきっかけにもなりかねません。
情報に踊らされてしまう
ある1つの事柄に対して複数の情報があった場合、取捨選択を行えなければ情報に振り回されてしまいます。
何かを判断するために情報を集めていたのに、肝心の情報が信頼できるか定かではない場合、手間が増えるリスクがあります。
また、情報が入るたび自分の意見を二転三転させていると、周囲から「主張に一貫性のない人」と判断されてしまうおそれもあるでしょう。
誹謗中傷によるトラブル
SNSが発展した現代では、匿名による誹謗中傷のトラブルも増えています。
秘匿性の高さゆえに直接的な誹謗中傷へのハードルが下がってしまっている点だけでなく、誹謗中傷にあたる投稿を拡散することも名誉棄損に該当するケースがあることは意外と知られていません。
安易な投稿や拡散によって訴訟に発展してしまうリスクを回避するためにも、メディアリテラシーを身につけることが大切です。
情報漏洩
メディアリテラシーの低さは、セキュリティ意識の低さにも直結します。
セキュリティインシデントは、企業の信頼を大きく損なう可能性がある重大なリスクです。
その重大なリスクを引き起こす原因を未然に防ぐためにも、メディアリテラシーを身につける必要性があります。
例えば次のような具体例が該当します。
・会社PCでスパムメールを開封し、企業システム全体がマルウェアに感染する
・リモートワーク中にVPNに接続せず、無料Wi-Fiに接続したことで情報を盗み見される
・有害なWebサイトにアクセスし、ウイルスソフトをダウンロードする
いずれもメディアリテラシーを身につけることで防げるインシデントです。
また企業では、外部要因だけでなく内部の不正などによる情報漏洩にも注意が必要です。
個人情報の特定
SNSでは、さまざまな要因で個人情報が特定されることがあります。
例えばアカウントの乗っ取りやなりすましアカウント、画像を投稿したタイミングや瞳に映った看板や電柱の文字で居住地を特定されるなど、いずれも実際に起こっている事例です。
画像に映る建物だけでなく、屋内の様子や反射による映り込み、地域行事などでも生活範囲が特定できることもあるため注意が必要です。
また企業では、従業員による画像投稿で企業の内部情報が漏れてしまう、プライベートなアカウントで悪意のある発言をしたことにより、投稿を遡られて勤務先が特定されクレームが届くなどの事例もあります。
このように、メディアリテラシーを身につけることで防げるリスクも多いことが、メディアリテラシーの必要性を向上させています。
\ 自分に合う働き方が分かる! /
メディアリテラシーを身につける方法
信憑性の高い情報源(ソースやデータ)を最優先する
情報を集める際の基本として、政府や専門機関が公式に発表しているものを最優先で調べましょう。
公的な団体が発表している資料の多くは、不特定多数の人に公開しても問題ないと判断されたものです。
また、調査対象の属性や人数、調査期間等も明示されている場合が多いため、比較的信頼できる情報源といっても差し支えありません。
不十分な部分や疑問が残る点もある場合は、これらの情報をベースとした調査・分析を探すことで足りないポイントを補いましょう。
参考データや参考文献等の表記を確認する癖をつける
上記に挙げた信憑性の高い情報源以外にも、有用な情報があるのも事実です。
信頼できるかどうかを判断するときには、その情報に参考データや参考文献等が明記されているかを確認しましょう。
複数の資料を参考にしているもの、新しいデータを取り入れているものは有用性が高い傾向があります。
ただし、あくまでも自分で情報を選ぶときの判断基準の1つとして扱うことが大切です。
命に関わることや人生を左右することなど、専門性の高い分野については自己判断をするのではなく、必ず専門家に尋ねましょう。
同じ情報でも複数の情報源からデータを集積・比較する
1つ事柄に関する情報でも、複数の情報源からデータを集めることをおすすめします。
これは前述した通り、メディアによって伝える内容に差が生じている可能性があるためです。
いくつかの情報を組み合わせることで、全体像が見える場合もあります。
情報収集の際には、できるだけ多くのところからデータを集めて比較しましょう。
\ IT転職のプロが無料でサポート! /
自分の目で情報をしっかり吟味しよう
自分で情報を見極めるのは簡単なことではありません。
しかし、普段から「自分は今どういう情報を必要としているのか」「どのような情報であれば信憑性が高いのか」を意識することで、適切な情報を選びやすくなります。
メディアリテラシーを身につけることは、社会人としても必須です。
現代ではインターネットから完全に切り離された職種は多くはないため、身につけておきましょう。
「エンジニアとして上流工程に携わりたい」
「IT業界に転職して年収を上げたい!」
「もっとモダンな環境で働きたい!」
などのキャリアのお悩みは是非、「IT・Web業界の知見が豊富なキャリアアドバイザー」にご相談ください!
IT特化の転職エージェントのGeekly(ギークリー)なら、専門職種ならではのお悩みも解決できる専任のキャリアアドバイザーがカウンセリングから入社後まで完全無料で全面サポートいたします!
転職しようか少しでも悩んでいる方は、お気軽に以下のボタンからご相談ください。
\ IT転職のプロが無料でサポート! /
あわせて読みたい関連記事
新着記事はこちら
-
- AI企業ランキング日本版!売上高・平均年収・離職率トップ5は?
-
2025/4/1
- AI
- ランキング
- 業界紹介
-
- 「SKYFLAGを世界一のプロダクトへ」挑戦を続けるSkyfallのプロダクト本部が語る今後の展望とは
-
2025/3/28
- 事業インタビュー
- 株式会社Skyfall
- 特集
-
- 【アンケート調査】今の会社を選んだ理由や、企業選びで重視する要素とは?
-
2025/3/28
- IT転職
- アンケート調査
- 特集
-
- なぜ書類選考で落ちた?ショックを受けなくても大丈夫な理由を解説
-
2025/3/27
- IT転職
- 書類選考
- 転職ノウハウ
-
- 技術だけでは終わらせない。事業と会社を動かすエンジニアの挑戦。新しい価値を生み出し、会社の未来を創る。ナハトでのエンジニアの働き方とは
-
2025/3/17
- 事業インタビュー
- 株式会社ナハト
- 特集
-
- インフラエンジニアの自己PR例文|経験者・未経験者向けの書き方やポイントを解説
-
2025/2/28
- IT転職
- インフラエンジニア
- 職種解説


 関連リンク
関連リンク